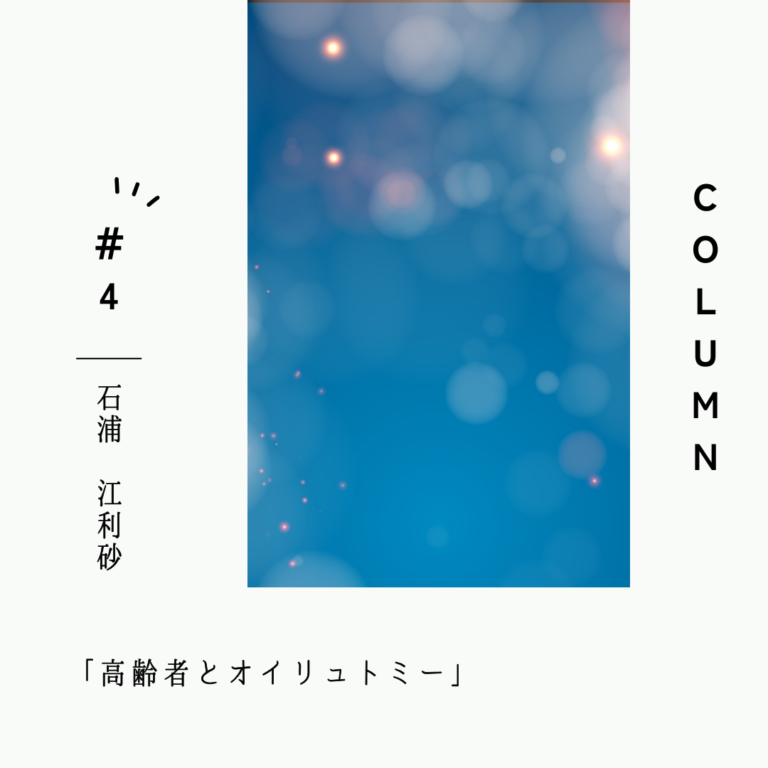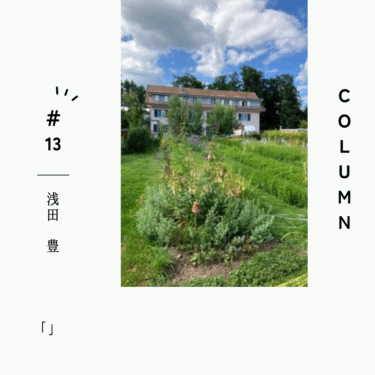お年寄りは模倣の天才
私の勤務先のひとつに、お寺に併設されている、小規模高齢者デイサービスがある。他の職員とともにご利用者のケアをする仕事のほか、日々の体操を担当させてもらっている。体操とは言うものの、オイリュトミストの私が行っている動きにはオイリュトミーの要素がたくさん入っている。
立つことが難しい方もいるし、転んで骨折するリスクを避けるために、始めから終わりまで椅子に座ったまま、足の上下などの簡単な動作を皆で行う。「ゆっくり上げて、ゆっくり沈めてゆきます」などと声をかけ、自分の脚に自分の自我がしっかり行き渡るようなオイリュトミー的動きに導いていく。生命を強化する子音のBの動きなど、いわゆる体操とは一線を画する動きもある。「オイリュトミーとは」などという説明は、一切しない。
そんな風変わりな体操であるが、皆さんは何の疑いもなく、喜んで動いて下さっている。幼児とオイリュトミーをするときのたいへんさは、ここにはない。お年寄りは、実は模倣の天才なのだ。

生きる力が息を吹き返していく
デイサービスのご利用者には認知症の方も多く、皆、多かれ少なかれ老いることへの不安を抱えているのは言うまでもない。そのような方たちに必要なのは、生命の覆い(エーテル体)を、もう一度身体全体にしっかりまとわせることである。
高齢者の、浅くなって胸だけで行っている呼吸を深く全身に行き渡らせ、足先から頭の先まで酸素が運ばれるようにするには、Lの動きを用いる。腕を大きく回すように動かしながら、上方に伸びた上半身を、今度は床に届くほど深く下ろしていく動き。これを座ったまま繰り返すだけで、お年寄りの顔が上気し、バラ色に変わってくる。皆、口々に「暑くなったね」と言い合っている。
巻き舌で「ルルル~」と発しながら腕と身体を前後に回転するように動かすRは、子どもたちが大好きな動きだが、お年寄りも大好きであることがわかった。この動きが始まると、自然に顔がほころんできて、ゲラゲラ笑ってしまうのだ。この動きが胃腸を活発にし、食欲を活性化させることで、生きる力が息を吹き返すのである。
そして何より大切なのは、こうした動きを通して気持ちが持ち上がってくることである。

オイリュトミーは魔法の体操
このように、6年以上にわたるこの仕事を通して私は、高齢者と幼児がよく似ていることを発見した。同時に、まったく正反対な特徴も見いだした。
幼児は、今日できなかったことが明日にはできるようになるという成長の原則のなかで生きているのだが、お年寄りは逆に、今日できていたことが明日にはできなくなるという厳しい現実を受け入れなければならない。もちろん、今日できることを明日もできるように支えるという視点ももちながら、朗らかに、前向きに老いを受け入れていくことの同伴者であることを、私は大切にしている。オイリュトミーは、お年寄りにそのような気分を理屈抜きで運んできてくれる、魔法の体操なのである。

石浦江利砂・キャサリーン
プロフィール
オイリュトミー療法士
介護初任者研修修了
アメリカ カルフォルニア州にある、サクラメント ルドルフ シュタイナーカレッジにて、アントロポゾフィーと出会い、2年間基礎を学ぶ。
その後、イギリス ペレドア スクール オブ アートにて、4年間のオイリュトミー養成コースを修了し、日本に帰国。導かれるように、子どものクラスを担当し、そこで出会った子どもたちがきっかけで、オイリュトミー療法士の資格を取得。
現在、東京、横浜、松本、名古屋の幼稚園・保育園にて教えるかたわら、ひだまりクリニック、神之木クリニック、高齢者施設にて勤務している。